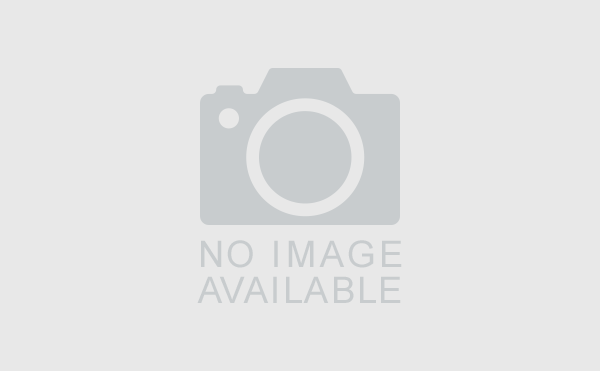親の借金を相続しないための相続放棄等の方法まとめ
親が亡くなると遺された遺族は亡くなった人が所有していた財産を分け合うことになります。 これが「相続」と呼ばれるものです。
世間でよく言われる「親の遺産を相続したから大金を手に入れた」というような話にもあるように、遺産を相続すれば大金が手に入ると勘違いしている人がとても多いです。
実際には、親が遺した遺産が資産に関わるものだけではなく、借金のように負債を残して亡くなった場合は、相続をした人に対して請求されるということもありうるのです。
そのようなことは子どもには酷な結果となりますので法律は様々な方法を用意しております。
このページでは、その親の残した遺産が借金である場合にそこから逃れる方法についてお伝えいたします。
目次
法律上親の債務を払わなければならない法律はない
法律では、親であっても他人であるので、その借金・債務を支払わなければならないということはありません。同居の有無ももちろん関係ありません。
しかし、連帯債務や連帯保証人となっているような場合には支払う義務があるのです。
仮に、勝手に連帯保証人にされていたような場合でも、本人の承諾なしに連帯保証契約を結ぶことはできないことになっています。
そのような場合には連帯保証債務は存在しなかったとして訴訟をおこすことも可能です。
相続をしてしまうと、それは自分の債務になる
上記のとおり、親であっても他人である以上、借金・債務の支払い義務はありません。しかしながら、仮に親御さんが無くなられた場合には、相続が発生します。
その結果親の残した借金であっても、必要な手続きをとらなければ、自分の借金となってしまいます。
以下では親の借金を継がない方法は生前と死後に分けてお伝えいたします。
まだ親が生きているうちに借金を相続しない方法

このページをご覧いただいた方には、「親の遺産を相続するといっても借金しかないはず、今から何とかできないか?」という事を考えていらっしゃるかもしれません。
そこで生前に借金を整理しておく方法を検討しましょう。具体的には主に3種類の方法があります。
任意整理
消費者金融や銀行から借り入れをしている場合には、利息を合わせて支払わなければなりません。
そこで、利息をカットして残った元金のみの支払いだけにしてもらう手続きが任意整理(にんいせいり)という方法があります。
依頼をする先は弁護士と認定司法書士です。相場は1社あたり2万円~5万円程度になります。
任意整理のメリットは
元金のみの支払いで済むようになるので、借金の返済が早くすすみます。ただし応じてくれるのは、消費者金融や銀行などの事業としてお金を貸している人だけですので、個人からお金を借りているような場合には交渉は上手くいきません。
また、借金を選んで交渉ができるため、住宅ローン債務や、連帯保証人がついている債務・抵当権がついているような債務には手を入れないということもできます。
任意整理のデメリットは
借金を返済することが前提の手続きなので、親に返済する収入があるか、家族で代わりに借金を肩代わりできる金銭がないとこの方法は取り得ないというデメリットがあります。
また、後述する自己破産・民事再生手続きに共通する債務整理全般的なデメリットとして、信用情報機関に事故情報として登録され(いわゆるブラックリスト)、5年~7年は借り入れをあらたに起こすことは難しくなります。
任意整理で借金を減らす手続き
- 弁護士・司法書士に借金の整理を依頼する。
- 弁護士・司法書士が借金の総額を確定する。
- 弁護士・司法書士が借り入れ先と交渉をして和解をする。
- 和解条項にしたがって支払いを始める。
- 借金の完済をする。
民事再生手続き

借金が多額で元本の返済が出来なくなるような場合には、借金額にもよりますが、負債を約1/5に減らしそれを3年(原則)でに支払っていく手続を民事再生手続き(みんじさいせいてつづき)と呼んでいます。
民事再生手続きのメリット
後述する自己破産では自宅を失いますが、こちらは自宅を失わずに債務を減らすことができるというメリットがあります。
また同じく自己破産では資格制限があるので、警備員などの職業につけないなどのデメリットがありますが、民事再生手続きをとることで、これらのデメリットを回避することができます。
民事再生手続きのデメリット
住宅ローンをのこす場合であっても、それ以外の理由で民事再生手続きを取る場合であっても、1/5程度の借金は残ることになるので、それは確実に支払わなければならないのがデメリットです(例外的にハードシップ免責という制度がありますが、きわめて例外と考えてください)。
また、民事再生手続きをとることになると、民事再生手続き開始決定時・書面決議時・最後の認可決定時と3度にわたって国の新聞である官報に載ることになります。ただし、官報を見ている人はそう多くはなく、官報から人にわかってしまう可能性はほぼ皆無と見ていいでしょう。
さらに前述した通り、債務整理手続きに共通してのデメリットは信用情報機関に事故情報として登録されることになります。民事再生手続きにおいては約7年~10年とされています。
民事再生手続きの相場は
依頼をするのは同じく弁護士・司法書士になります。相場としては20万~60万(住宅があるかないかで相場が大きくかわってきます)程度です。
民事再生手続きをすると借金はどうなるか?
前述もしましたが、借金の総額にもよりますが、負債を約1/5に減らしてそれを原則3年分割で支払っていくことになります。裁判所によって再生計画を定められることになるので個人の借り入れがあるような場合でもこの計画にしたがって回収をすることになります。
相続を見据えた民事再生手続きはどのように使うか?
任意整理では支払いきれないけれども、1/5まで借金が減れば完済ができるような場合には民事再生手続きを利用するメリットは大きいでしょう。
ただし、1/5に圧縮されたものでも借金は返し続ける手続きではあるので、親に収入があることが条件であることに代わりはありません。
民事再生手続きで借金を減らす手続き
- 弁護士・司法書士に借金の整理を依頼する。
- 弁護士・司法書士が借金の総額を確定する。
- 弁護士・司法書士が裁判所に申立てをする書類を作成する
- 裁判所において民事再生手続き開始の決定をする。
- 再生計画にしたがって債務の弁済をしていく。
自己破産手続き

借金が多額で、収入もない、あったとしても乏しいような場合に、借金をなくしてしまう制度の事を自己破産手続き(じこはさんてつづき)といいます。
自己破産手続きのメリット
親が高齢で年金生活+α程度の生活をしているような場合には多額の借金の返済に窮していることが多いでしょう。
自己破産手続きでは、税金などの一部の債務を除いてほとんど全ての債務をなくしてしまうことができる点が大きなメリットです。
自己破産手続きのデメリット
民事再生手続きのところでもすこしお伝えしましたが、自己破産手続開始決定から免責決定までの間に、資格の制限や住所の移動の制限、管財事件という複雑な事件になった場合には郵送物がすべて転送されることになっているなどの各種の制限があることがデメリットです。
また、破産手続開始決定時と免責決定時の1回ないし2回、官報に名前が載ってしまうことです。
さらに、債務整理手続き全般的なデメリットとして、信用情報機関に事故情報として登録されてしまうことになります。自己破産の場合の期間は民事再生手続きと同じく7年~10年とされています。
自己破産手続きの依頼先・相場
専門家に依頼をする事になります。依頼先は同じく弁護士・司法書士に依頼をすることになります。相場としては15万~60万程度でしょう。相場の幅は同時廃止という簡易な手続きで済むか、少額管財という複雑な手続きを要するかによります。
自己破産手続きをすると借金はどうなるか?
自己破産手続きをすると借金は原則として支払いをする必要がなくなます。税金などの一部の負債については免責がされません(負債が残ることになります)。
相続を見据えた自己破産手続きはどのように使うか?
前述もしましたが親が高齢で収入に乏しいく、遺したい家・土地がないような場合には、自己破産手続きを利用すべきでしょう。
自己破産手続きで借金を減らす手続き
- 弁護士・司法書士に借金の整理を依頼する。
- 弁護士・司法書士が借金の総額を確定する。
- 弁護士・司法書士が裁判所に申立てをする書類を作成する。
- 裁判所において自己破産手続き開始の決定をする。
- 債権者集会or免責審尋のために裁判所に出頭する。
- 裁判所の決定で免責となる。
借金の債務整理手続きに向いている人・そうではない人

親に借金がある場合にどのような場合に債務整理をすべきでしょうか?
これからまだ親が長生きしそうであれば債務整理を
親がこれからも長生きをしそうだということであれば債務整理手続きの利用をしてもらいましょう。親の生活も楽になるはずです。
余命が長くないならば相続放棄を検討
債務整理手続きはそれなりに費用がかかります。これに対して、相続放棄は専門家に依頼しなくてもできますし、依頼をする場合でも依頼費用は高額にはなりません。
ですので相続放棄を検討しましょう。
親が亡くなったときの借金の調べ方

親が亡くなったときに借金があるかどうかをどのようにして調べればよいでしょうか?
銀行・消費者金融・クレジットカードの残高があるかどうかを調べる
各金融機関に直接聞いても、個人情報保護の観点から教えてくれることはまずないと考えるべきでしょう。
しかし、故人の銀行・消費者金融・クレジットカードの残高を調べることは「信用情報機関」に照会をすることで、行うことができます。
信用情報機関については全国銀行個人信用情報センター、株式会社シー・アイ・シー、株式会社日本信用情報機構(JICC)の3社があります。
念のためこの3社から情報を得て、信用情報機関に載る借金の情報を取得してください。
ただこれらの情報はあくまで本人が亡くなった後に家族が取得できるものであることは注意をしてください。
個人間の借金・連帯債務・連帯保証債務など
調査が難しいのは、こういった信用情報機関に載らない債務です。
個人間の借金や、会社を運営している場合の会社の連帯債務や他の会社の連帯保証債務などが挙げられます。
これらについては個人的な人間関係や、会社の取引先などに徹底的にヒアリングをするしかないということになります。
親が亡くなった後に親の借金を負わないようにするには?
このページにたどりついている多くの方がすでに親が亡くなってその借金をどうすればいいかと悩まれているのではないでしょうか?
そのような場合には、「相続放棄」と「限定承認」という2つの方法があります。
相続放棄とは

相続放棄とは、法律で定められた手続きをすれば、はじめから相続人ではなかったことになる制度のことをいいます。
「はじめから相続人ではなかった」ことになる事によって借金を相続することもありませんし、相続争いに巻き込まれることもありません。
相続放棄のメリット
「はじめから相続人ではなかった」という扱いになるので、被相続人が持っていた一切の財産や負債などを承継しなくてもすみます。被相続人が自己破産手続きを行って相続した場合には一定の負債(税金など)は相続する事に比べると、一切なにも相続しなくなる点、手続きが簡単な点で優れています。
相続放棄のデメリット
相続放棄をしてしまったら、何も主張をすることはできません。またやっぱり相続放棄しなかったことにする、ということはできませんので注意が必要です。
相続放棄は特定の人に継がせたい・争いに巻き込まれたくないという理由でも利用できる。
ここまでは「親に借金があってそれを継ぎたくない」という事をメインに相続放棄をお伝えしてきましたが、親に借金があること以外の理由でも相続放棄をする事は可能です。
例えば、一家で事業を営んでいて誰か一人に財産を集中させたい、という理由で相続放棄をすることも、単純に相続するよりも争いに巻き込まれたくないという理由で相続放棄をすることも可能なのです。
遺産分割協議で持分を無しにすることで「事実上の相続放棄」もできる。
相続放棄と言っても、後述する家庭裁判所を解した法律的意味の相続放棄の他に、事実上の相続放棄をする方法もあります。
それは、遺産分割協議で持分を0にする方法です。この場合、債務がある場合には債務に関しては引き継ぐ点で注意が必要です。
借金があるかどうかわからない場合には限定承認という方法もある。
相続放棄をしたい理由の多くが「相続財産が借金だけ」という理由ですが、そもそも論として借金があるかどうかわからない場合はどうすればよいでしょうか?
この場合、限定承認と呼ばれる、同じく家庭裁判所を通じて行う手続きを利用することによって、相続自体はするが、借金は相続財産の範囲内でしかしないということができるようになります。
こんな場合には相続放棄はできなくなる。
相続放棄をする以上は、守らなければならないルールがあります。遺産に手を付けたりであったり、相続放棄後でも財産の隠匿行為を行ったりすると、相続を承認したとみなされてしまい、相続放棄ができなくなってしまいます(この制度を法定単純承認といいます)。
相続放棄の手続きはこうする

至急、財産(負債)の調査をする。
相続放棄には原則相続開始から3ヶ月以内にしなければならないという期間制限があります。ですのでなるべく早い段階から借金などの負債がどのくらいあるかを調査する必要があります。
消費者金融や銀行のカードローンなどに関しては、「信用情報機関」といわれる会社から情報を得ることによってわかります。
亡くなった方が個人事業や小さな株式会社を営んでいたような場合には、取引先の連帯保証債務になっていないかを当事者にヒアリングをしたり、契約書類等を捜すなどしてチェックしておきましょう。
どこの裁判所に申し込めばいいかを調べる(管轄)
相続放棄の手続きは家庭裁判所で行いないます。家庭裁判所も全国にあるので、どこの家庭裁判所に申し込めばよいかという問題が次に発生します(「管轄(かんかつ)」の問題といわれます)。
これは被相続人の最後の住所地を担当している家庭裁判所が申込みを受ける権限、つまり管轄があるとされています。住所地と担当している裁判所のエリアに関しては裁判所のホームページで確認することができます。
相続放棄の申込をする。(申述)
相続放棄の申込みをします。この申込みのことを「申述(しんじゅつ)」と法律用語では言っております。
申述の際は書面で行います。ですので申述書を提出します。
また同時に添付書類としては
・被相続人の住民票の除票か戸籍附表
・相続放棄をする人の戸籍謄本
以上の2点に加えて、相続する人との関係に応じて戸籍謄本や改正原戸籍等が必要となります。
<ul class="related"> <li>『<a href="https://all-souzoku.com/article/221/">相続放棄に必要な書類リスト</a>』</li></ul>
裁判所からの問い合わせを受ける(照会)
相続放棄の申込みを行うと、裁判所から問い合わせが通常は文書で来るので、それに回答をすることになります。この問い合わせの事を「照会」といいます。
内容としては、自分の意思で相続放棄をするのか?なぜ相続放棄をするのか?といった事等が聞かれますので、書面でそれに返答をする事になります。
相続放棄を受け付けた証明書類をもらう。
家庭裁判所は照会した内容をもとに検討をして問題がなければ相続放棄の申込みは受理をされます。
この時に出される書面の事を「相続放棄受理証明書」と呼んでおり、通常はその写しを債権者に渡すことで負債の追求から免れることができます。
3ヶ月を超えても相続放棄ができる場合がある。

相続放棄の原則は相続が発生したときから3ヶ月以内です。
借金を回収する担当の仕事についている人なら基本的にはこのことを考慮して3ヶ月を経過してから請求をしてくることが通常です。
よって3ヶ月経過後に借金が発覚する事も珍しくはありません。
そこで例外的に3ヶ月経過後でも相続放棄ができる場合があります。具体的には、「3ヶ月以内に相続放棄をしなかったことに理由があれば」可能となります。
相続放棄の申述の際にはなぜ3ヶ月以内に相続放棄をしなかったかの理由を要求されることになります。
きちんと説明できなければ相続放棄が出来なくなってしまいます。専門家に依頼をするべきケースとなるでしょう。
専門家への依頼の仕方と相場
裁判所に提出する書類のため、弁護士か司法書士に依頼をする事になります。最近では司法書士が活躍するケースも目立ってきました。
相続開始から3ヶ月経過をしていない案件で安い事務所ですと10

相続手続きを自分でやるための方法、相続に関する知識などの情報を発信しています。
副業、プチ起業、スキルアップにおすすめ!アート・クラフトの講師になれる認定講座

世界中で大人気、NYやLAでは「第2のヨガ」と呼ばれる新しいアート・DIYのレッスン方法を学んでみませんか?
副業、プチ起業、スキルアップにおすすめ、講師として教えられるようになる「ペイントインストラクター認定講座」「DIYインストラクター認定講座」の講師が全国で誕生中!